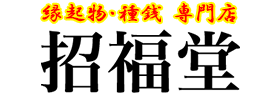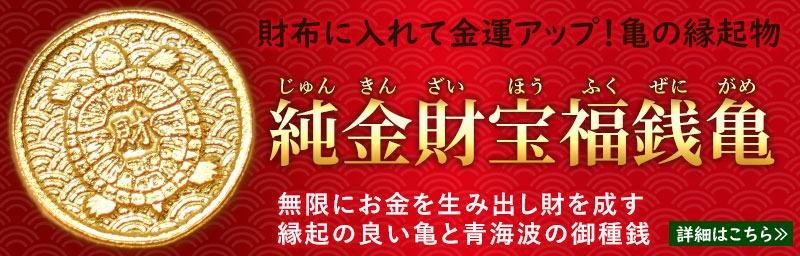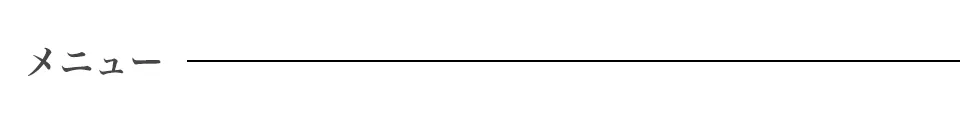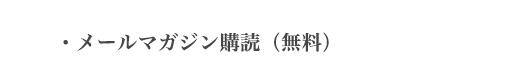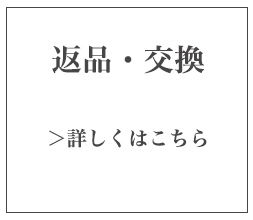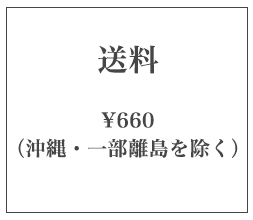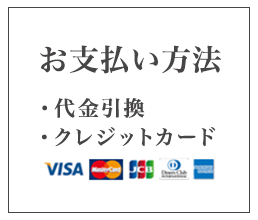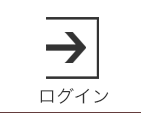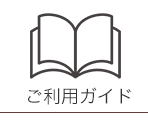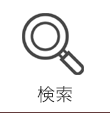福を呼ぶ「縁起物」とは?動物や日本の伝統的な縁起物の一覧と意味

「縁起物」は、古くから日本で運気を高めるために用いられてきたアイテムです。
商売繁盛、健康長寿、家庭円満など、それぞれの願いに合わせた縁起物があり、日常生活のさまざまな場面で活用されています。
この記事では、縁起の良い動物やアイテム、食べ物についてご紹介します。
「最近ツイてないな」「もっと運を良くしたい!」「新しいことに挑戦したい!」
そんな時には、縁起物を取り入れてみるのもひとつの方法です。
自分に合うものを見つけて、毎日を前向きに過ごしてみましょう。
縁起物とは?

縁起物とは、幸運や成功、健康、金運などを引き寄せると信じられてきたものです。
昔から人々の暮らしの中に自然と取り入れられており、お守りや飾り物、食べ物としても身近な存在です。
例えば、長寿を象徴する「鶴と亀」、商売繁盛を願う「招き猫」、財運を招く「打ち出の小槌」など、それぞれに意味があります。
また、おせち料理のように特別な日に食べる食べ物や、普段口にする食材にも縁起を担ぐものが多くあります。
縁起物はただの飾りやお守りではなく、願いごとや前向きな気持ちを後押ししてくれる存在です。
身近に取り入れることで、気持ちが整ったり、新しいことに挑戦するきっかけになるでしょう。
縁起の良い動物・生き物一覧と意味

昔から、動物はそれぞれ特別な意味を持つ存在として考えられてきました。
ここでは、縁起の良い動物や生き物と、それぞれの意味についてご紹介します。
鶴・亀(長寿・健康)
「鶴は千年、亀は万年」と昔から言われるように、どちらも長寿の象徴です。
鶴は優雅な姿で、夫婦で一生を共にすることから、夫婦円満の意味も込められています。
亀は硬い甲羅とゆったりとした動きが特徴で、安定感や粘り強さを連想させます。
お正月やお祝いごとでよく見かけるモチーフで、着物の柄や工芸品にもよく使われています。
龍(成功・出世)
龍は、勢いよく天に昇る姿から、運気をグッと押し上げてくれる存在として人気があります。
水や雨を司る存在ともされ、龍は恵みの雨をもたらすことで作物が育ち、生活が豊かになることから、繁栄や発展の象徴としても大切にされてきました。
龍の置物や絵を飾ることで、仕事運や出世運を後押しすると言われています。
新しいことにチャレンジする時や、大きな目標に向かって頑張りたいときに、心強い味方となるでしょう。
龍は、成功や出世を目指す人におすすめの縁起物です。
フクロウ(学業・金運)
フクロウは「不苦労(ふくろう)」と読めることから、苦労を避ける縁起の良い鳥とされています。
また、「福来朗(ふくろう)」とも書かれ、幸福を呼び込む存在としても親しまれています。
西洋では知恵の象徴とされ、学問や知識を深めるシンボルとしても大切にされています。
そのため、受験生や勉強を頑張る人、金運アップを願う人など、幅広い人から縁起物として選ばれています。
へび(財運・脱皮による成長)
へびは古くから財運を呼ぶ生き物とされ、特に白蛇は弁財天の使いとして金運アップにご利益があると言われています。
へびの抜け殻を財布に入れておくと金運が上がる、という言い伝えもあります。
また、へびは脱皮を繰り返して成長することから「再生」や「新たな自分への変化」を象徴し、新しい挑戦に踏み出すときのお守りとしてもおすすめです。
金魚(富・繁栄)
金魚の鮮やかな赤や金色は、金運や繁栄の象徴とされています。
水の中を優雅に泳ぐ姿は、良い運気がスムーズに流れることをイメージさせます。
中国では、お金が余る「金余」、お金が思い通りになる「金如」と、きんぎょが同じ発音なところから、豊かさをもたらす存在として親しまれています。
鯛(幸福・祝い事)
「めでたい」という言葉にも使われている鯛は、日本のお祝いごとに欠かせない存在です。
結婚式やお正月のおせち料理など、特別な場面で鯛が登場するのは、鯛の華やかな姿が成功や豊かさを象徴しているからです。
焼き鯛などのお祝い膳だけでなく、鯛の形をした和菓子やお守り、熨斗紙のデザインにも使われ、商売繁盛や家庭円満への願いが込められています。
鯨(大きな成功・富)
鯨は、大きな体と悠々と泳ぐ姿から「大きな成功」や「豊かさ」の象徴とされています。
広い海を自由に泳ぐ姿は、余裕や安定感をイメージさせ、物事に動じず前進する力強さを表しています。
鯨モチーフのアイテムは、挑戦したいことがある人や、目標に向かって大きな成果を目指す人におすすめです。
アクセサリーや雑貨などで取り入れることで、前向きな気持ちを後押ししてくれる存在になるでしょう。
鯉(出世・努力)
鯉は、努力と挑戦の象徴です。
「鯉の滝登り」という伝説では、激しい滝を登り切った鯉が龍へと変わり、努力の先に大きな成長や出世が待っていることを表しています。
端午の節句に飾られる「こいのぼり」には、子どもが元気に育ち、たくましく成長するよう願いが込められています。
力強く泳ぐ姿は、目標に向かって前進する姿勢と重なります。
挑戦する気持ちを後押ししたい時は、鯉のデザインが入った置物やお守り、絵柄などを取り入れてみてはいかがでしょうか。
うさぎ(飛躍・繁栄)
うさぎは、ぴょんぴょんと跳ねる姿から「飛躍」の象徴とされ、新しいことに挑戦したい時や、ステップアップを願う人にぴったりです。
また、子どもをたくさん産むことから、豊かさや繁栄の意味もあります。
さらに、うさぎは月と深い関わりがあり、神秘的な存在としても知られています。
特に白いうさぎは幸運のシンボルとされ、恋愛成就や家庭運アップを願うお守りとしても人気です。
かえる(金運・無事帰る)
かえるは、「お金が帰る」「無事に帰る」という言葉にかけて、金運アップや安全を願う縁起物として親しまれています。
旅行や出張のお守り、子どもの交通安全のお守りとして人気があり、無事に帰宅できることを願う意味が込められています。
金運アップを願うなら、金色のかえるの置物や、財布に入れる小さなかえるのチャームがおすすめです。
運気を上げる縁起物アイテム一覧

縁起物のアイテムには、それぞれに込められた意味があります。
目標達成、商売繁盛、金運アップなど、自分の願いに合わせて取り入れることで、前向きな気持ちを後押ししてくれるでしょう。
だるま(目標達成・開運)
だるまは、「七転び八起き」の精神を象徴する存在です。
どんな困難にも負けず、何度でも立ち上がる強さを表しています。
願い事をする際は片目を描き、達成したらもう片方の目を入れることで、自分の努力と成果を目に見える形で確認できます。
色によってご利益が異なり、赤は開運、黄色は金運、青は学業成就、ピンクは恋愛運です。
アップしたい運気によって色を選びましょう。
招き猫(商売繁盛・幸運)
招き猫は、手招きのポーズから「福を招く」として親しまれています。
右手を挙げている猫は「金運を招く」、左手を挙げている猫は「人との良い縁を招く」「お客を招く」という意味があります。
お店や家庭の玄関に飾られることが多いですが、最近は小判や種銭にデザインされたものもあり、金運のお守りとして人気があります。
白は開運招福・商売繁盛、黒は厄除け・魔除け、金色と黄色は金運、赤は健康運、青は学業成就、ピンクは恋愛運、緑は家内安全と、色によって込められている意味が異なります。
七福神(幸福・財運)
七福神は、名前の通り「幸福」と「財運」をもたらすとされる7人の神さまの集まりです。
恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁財天、福禄寿、寿老人、布袋の神さまが、それぞれ異なるご利益を持ち、豊かさや繁栄を象徴しています。
七福神の絵や置物を飾ることで、商売繁盛や金運アップのご利益があるとされ、新年に「七福神巡り」をすることで一年の運気が高まると考えられています。
富士山(開運・長寿)
富士山は、日本一の高さを誇る山で、開運や長寿の象徴とされています。
特に初日の出と一緒に見る富士山は縁起が良いとされ、新しい年の幸せを願う特別な風景を見るために訪れる人もいます。
また、富士山の絵や写真を飾ることで、運気が上がると言われています。
特に、仕事や目標の達成を願う人にとって、富士山のパワーは心強い味方になってくれるでしょう。
扇子(繁栄・成功)
扇子は、末広がりの形から「繁栄」や「成功」の象徴とされています。
広がる形が運気の拡大を表すことから、商売繁盛や事業の発展を願って飾られることが多いです。
特に金色や赤色の扇子は縁起が良いとされ、開運や金運アップを願う際のインテリアとしても取り入れられています。
打ち出の小槌(財運・願望成就)
打ち出の小槌は、一振りすることで願いが叶うとされる財運の象徴です。
日本の昔話「一寸法師」にも登場し、振ることで欲しいものを生み出し、豊かさをもたらす力があると伝えられています。
商売繁盛や収入アップを願う人から人気で、財布や金庫の近くに置くことで金運を引き寄せると言われています。
羽子板(厄除け・健康)
羽子板は、邪気をはね返す縁起物として親しまれており、女の子の健やかな成長を願う贈り物として選ばれることが多いです。
特に初正月のお祝いとして贈られ、健康と幸せへの願いが込められています。
お正月の羽根つきには、羽根を打つことで邪気を遠ざけ、無病息災を願う意味があります。
そのため、羽子板をお正月飾りとして飾ることもあり、華やかなデザインの羽子板は健やかな成長や家族の健康を願う縁起物としても楽しまれています。
熊手(金運・商売繁盛)
熊手は、福を「かき集める」道具として、商売繁盛や金運アップを願う縁起物です。
特に、酉の市で販売される豪華な装飾のついた熊手は、新たな一年の繁栄を願って多くの人が購入します。
店先やオフィスに飾ると、事業の成功や財運向上が期待できます。
古い熊手は一年ごとに新調することが大切。
毎年、新しい熊手で新しい運気を取り込むようにしましょう。
熊手(金運・商売繁盛)
熊手は、福を「かき集める」道具として、商売繁盛や金運アップを願う縁起物です。
特に、酉の市で販売される豪華な装飾のついた熊手は、新たな一年の繁栄を願って多くの人が購入します。
店先やオフィスに飾ると、事業の成功や財運向上が期待できます。
古い熊手は一年ごとに新調することが大切。
毎年、新しい熊手で新しい運気を取り込むようにしましょう。
種銭(金運アップ)
種銭とは、お金を増やすための「お金の種」のことです。
もともとは、縁起の良い金額を元手にして投資する風習があり、今では新しい財布に最初に入れるお金としても知られています。
種銭には、縁起の良い動物や七福神が描かれた金運モチーフのもの、手元の硬貨(特に「115円」が開運に良いとされる)を使う方法、そして神社で授かるものがあります。
金運アップを願う人には、金色の小さな種銭を財布に入れるのがおすすめ。
特に純金・純銀製など純度が高いものは、金運を引き寄せるパワーが強いと言われています。
お守り(厄除け・運気上昇)
お守りは、神社や寺院で授かるもので、厄除けや運気アップを願う人にとって身近な存在です。
学業成就、商売繁盛、健康祈願など、目的に応じたさまざまなお守りがあります。
肌身離さず持ち歩いたり、カバンや財布に入れておくことで、日常生活の中で心の支えとなります。
自分の願いに合ったお守りを選ぶことが大切です。
縁起の良い食べ物

縁起の良い食べ物も、古くから大切にされています。
例えば、お正月に食べる「おせち料理」は、一つひとつに意味が込められています。
黒豆は「まめに働く」、数の子は「子孫繁栄」、昆布巻きは「喜ぶ(よろこぶ)」など、言葉の響きや語呂合わせで縁起を担いでいます。
また、「長寿」を願うそばや、「勝負運」を上げるカツ(勝つ)、「金運」に良いとされる豆や栗など、日常の食事でも取り入れやすい縁起の良い食材があります。
お正月などの特別な日だけでなく、日頃の食事にもこうした食材を取り入れて、運気アップを意識してみるのもおすすめですよ。
縁起物の選び方と取り入れ方

縁起物を取り入れる際は、自分の願いやライフスタイルに合ったものを選ぶことが大切です。
例えば、仕事運を上げたいなら「龍」や「招き猫」、健康を願うなら「鶴と亀」や「お守り」、金運を上げたいなら「へび」や「種銭」など、目的に合った縁起物を選びましょう。
また、縁起物は飾る場所や使い方によっても効果が変わると言われています。
例えば、招き猫はお店の入り口や玄関に、打ち出の小槌はお財布の近くに置くのがおすすめ。
日々の暮らしの中で自然に取り入れられる方法を見つけて、気軽に運気アップを目指してくださいね。
まとめ

縁起物には、さまざまな種類があり、それぞれに意味やご利益が込められています。
動物やアイテム、食べ物など、自分の願いに合ったものを取り入れることで、日々の暮らしにちょっとした前向きな気持ちをプラスできます。
大切なのは、縁起物をただ持つだけでなく、その願いを意識しながら前向きに過ごすこと。
普段の生活の中に自然に取り入れながら、日々の運気を少しずつ上げていきましょう。